2人の子どもを育てるパパが「子育て・教育」について発信するこどもスタートラボです。
パパ・ママであれば子どもの成長や将来に良い影響を与えるために習い事や通信教育などの習い事を一度は検討し、「何をいつからさせたらいいのか」と頭を悩ませるものですよね。
我が家でも最近習い事を検討しました。その際に誰もが一度はこう思うのではないでしょうか?
「幼児教育はいつから始めるのがいいの?うちの子は早すぎ?それとも遅すぎ?」
子育てをしていると、多くのパパ・ママが一度は抱く疑問です。
早すぎても子どもに負担になるのではないか?
遅すぎて他の子と差がついてしまうのではないか?
そんな悩みを抱えるパパ・ママの疑問に答えるために、この記事では 幼児教育を始める適切な時期 について、実体験や世の中の公表資料、家庭でできる工夫を交えながら、わかりやすく解説していきます。
幼児教育の定義と目的 – 何をもって「幼児教育」というのか
幼児教育の定義
幼児教育とは、幼児(0歳から小学校入学前までの子ども)を対象とした教育を指します。
遊びや体験を通じて、知識だけでなく 思考力・感情・社会性 を育むことが目的です。
幼児教育の特徴
- 詰め込み学習ではなく「遊びの中の学び」
- 語彙力・表現力を伸ばす「ことばの刺激」
- 他者との関わりで育つ「社会性」
- 音楽・体を使った「感覚的学び」
つまり、幼児教育は「勉強させること」ではなく、人生の土台づくり なのです。
幼児期は脳が最も発達するゴールデンタイム
0歳幼児教育を考えるうえで大切なのは、脳の発達スピードです。
WEBで検索をするとたくさん出てくるのですが、人間の脳は 0〜3歳の間に約80%が形成される と言われています。参考になる情報はたくさんありますが、幼児教育を展開されているベビーパークからもコラムが出ておりました。
幼児教育の無償化の論点という、文部科学省が平成21年3月30日に公表した資料の中には、
「幼児期からの楽器演奏などの練習・訓練は脳に変化を起こすが、この変化は一定の年齢を過ぎると生じにくくなる」
「言語の習得にも感受性期が存在する可能性が高い。」
といった記載があり、幼児教育によってその後の子どもの成長に一定影響が出る可能性があることが記載されておりました。
この時期に受ける刺激や経験は、言語・社会性・感情のコントロールなどの基盤を作るうえで非常に重要なんですね。
調べてみて、こんなに多くの情報が出ていることに驚きましたし自分自身情報が多く悩みました。
言語の臨界期と教育のタイミング
言語習得には「臨界期」と呼ばれる時期があるそうです。私はまわりの先輩パパ・ママからきいて知りました。
皆さんがおっしゃっていたのは「英語は3歳までに始めないと身につきにくくなってしまう」または「早めに始めたほうが有利」ということ。
調べたところ、0〜6歳の間に多くの言語刺激を受けることで脳の言語野が柔軟に発達し、言語がスムーズに身につく時期を臨界期というらしいです。
- 0〜3歳:母語の基盤をつくる時期
- 3〜6歳:語彙力をぐんぐん伸ばす時期
臨界期仮説において、具体的に何歳までが「臨界期」にあたるのかは、研究者のあいだでもいろいろな見解があるようで、統一された結論はまだなく、現在も仮説の段階にとどまっています。ただ、一般的には、幼児期から思春期頃(12~13歳くらい)までが臨界期とされることが多いようです。
外国語は3歳までに始めたほうが良いは一理あるものの、「遅いということはない」、日本語で沢山話しかけてあげて意味を理解させることがかわらず第一優先で、余白があれば英語などの言語にも遊びで触れるといったかたちが良さそうだなと思いました。
年齢別おすすめ教育アプローチ
0〜1歳:五感と愛着形成
- 読み聞かせ:触れる絵本や布絵本で視覚・触覚を刺激
- 音楽:わらべ歌やクラシックで聴覚を育てる
- スキンシップ:マッサージや抱っこで安心感を与える
- 親の表情や声かけで愛着を育む
おすすめ教材例
- 音の出る絵本
- 赤ちゃん向けリズム遊び用マット
1〜2歳:言語と運動の基礎
- 生活習慣:手洗い・片付けなど簡単な自立行動
- 言葉:簡単な単語カード、日常会話で語彙を増やす
- 運動:公園遊び、走る・登る・投げるで体幹やバランスを鍛える
遊びのポイント
- 親子で一緒にやる
- 失敗しても笑顔でフォロー
- とにかく子どもが楽しいと思えるように
2〜3歳:好奇心と生活習慣の定着
- 数字や色、形の分類遊び
- 「なんで?」という質問に答える会話
- 簡単なお手伝いで自立心を育てる
家庭でできるアイデア
- なにか遠くのものをとってもらう
- 買い物に一緒に行って指定したものをとってもらってカゴに入れるお手伝い
- お片付けをゲーム感覚でおこなう
- 絵カードで数字や文字を楽しく学ぶ
3〜5歳:集団生活と学びの土台づくり
- 幼稚園・保育園での集団生活
- ルールを守る遊び(すごろく、カードゲーム)
- 習い事(英語、ピアノ、水泳など)の開始
習い事のポイント
- 興味に合わせて習い事を選ぶ
- 無理に多くやらせず、継続可能なペースで
- 家庭の生活リズムを第一に、無理せず継続可能な日程で取り入れる
- パパ・ママも子どもの習い事自体や子ども成長に関心を持ち、子どもに声をかけてあげる
失敗しない幼児教育のポイント
- 遊びを通して学ばせる – 「やらされている感」を避ける。子どもが楽しいと思えるように工夫する。
- 子どもの性格に合わせる – 競争好きか、マイペースか、集団が苦手か得意か。
- 短時間・高頻度 – 幼児は集中力が短いので長時間無理をさせない。生活の中に取り入れ繰り返し取り組んで習慣化する。
- 成果より過程を褒める – 自信を持たせる。親は認めてくれていると子どもが感じれる。親が子どもに対して安心感を与えてあげる。
我が家の実体験と感じたこと(2児パパの視点)
我が家では、外遊び全般、ブロック遊び、絵本、プラレール、ぬいぐるみ遊び、おままごと、一緒にピタゴラスイッチを作ってみる、TVや動画をいろんなジャンル見せてみるなど、沢山のことを子どもと一緒に行う中で、その子の適性や思考性、何がどこまでできるのかを観察して、何が好きか、得意かを妻と話し合ってこんなことが好きそうだねや、こんなことならできるのではないかなど話し合ってタイミング、習い事の種類、教材を選びました。
感じたのは、早く始めることがよいのではなく「その子の適性に合わせ、子ども側の準備ができたと思うタイミングで無理に押し付けず、家庭の生活リズムの中で無理せずやれる範囲で体験などから少しずつ始めてみる」ことのほうが大事だということです。
早く始めることを意識しすぎるあまりに、子どもの適性を無視したり、親の価値観を押し付けたり、生活リズムを乱してまで通ったりすることで、親も子もストレスを抱えてしまっては元も子もないと私は思います。
まとめ – 「いつから」よりも「どうやるか」が大切
結論として、幼児教育は何歳からでもOK。
大切なのは、
- 子ども1人1人の発達段階に合った内容であること
- 子どもの思考性や得意不得意を考慮すること
- 親も子も無理なく続けられる環境内で行うこと
- 決して親の価値観のみで子どもに押し付けないこと
です。
「早く始めなきゃ」と考えるより、まずは子どもの発達段階と思考性や得意不得意を理解してあげることです。
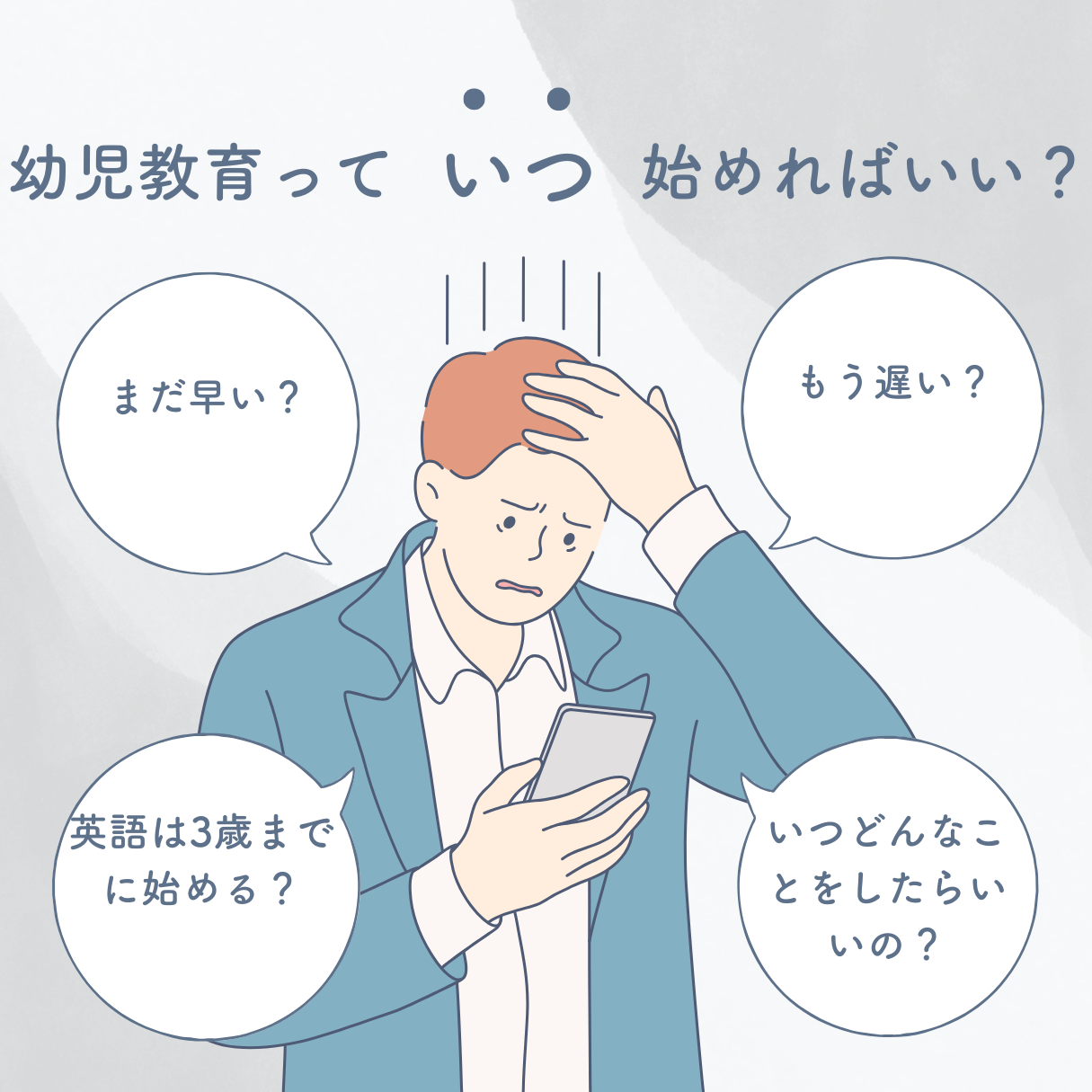
コメント